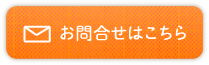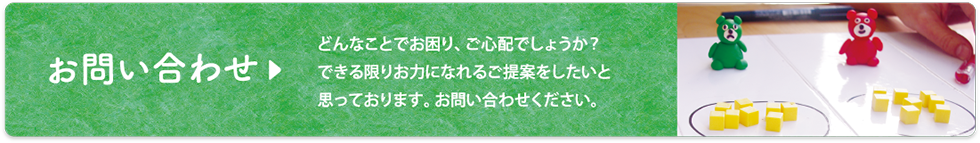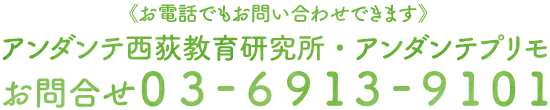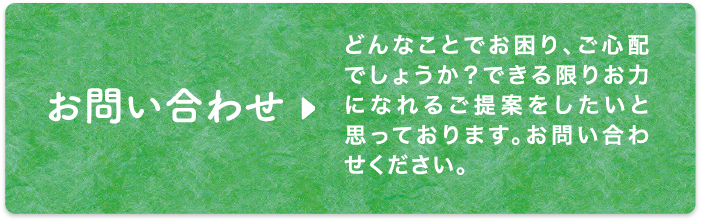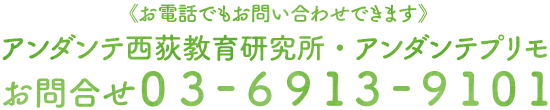新しい記事
- 2024.12.17 スタッフを募集中です。(株式会社リップルズ)
- 2023.12.20 金子は外でどんな仕事をしているのか?:アンダンテBackyard⑩
- 2023.11.15 アンダンテではどんな教材使ってる?:アンダンテbackyard⑨
人は、こんなにも、多様だ。
息子は4月から保育園の0歳児クラスに通っています。
先月で、クラスの全員が1歳になりました。
けさ、息子を送り届けて園を出ようとしたとき、ふと振り返って
一人一人の子どもたちのなんと多様なことか・・・と、あらためて感じました。
誕生日は順々に来るけれど、歩き始めたタイミングや、言葉が出始めるタイミングは、
決してその順序どおりではありません。
8か月ぐらいからすでに歩いていた子もいるし、1歳過ぎてもまだまだハイハイ主流の子もいます。
「ママ―」と呼んでいる子がいる一方で、うちの息子は「バー」(バナナのバであり、バスのバでもある)しか言わないな~と、ついこの間までは思っていたのが、この年末年始で一気にボキャブラリーを増やし、周囲がびっくりするほどお喋りさんになりました。
行事があると、慎重で意外と緊張しぃのわが子は毎回硬直している傍らで、活発で物怖じしないお友達が舞台に躍り出ます。
遊び方を見ていても、人との関わりが楽しい子もいれば、もっぱらモノをいじるのを好むわが子のようなタイプもいます。
性格も、発達のプロセスも、興味の対象も、
生まれてからほんの1年で、こんなにもちがう。
それは、あたりまえのこと。
なのに、ほんの数年もすれば、
○年生では、これだけの漢字を書けるようになる とか
○年生では、何ケタの何算をマスターしている とか
一定の年齢のくくりで一律の基準が引かれ、
その基準を物差しに、何が「できる」「できない」と、一人一人が評価されることになります。
ともすれば、学習の基準だけでなく、学習の方法や過程さえも一律なのが、
私たちが当たり前と思ってきた学校や授業のやり方です。
これだけ人が多様であれば、何かをできるようになるために必要な時間ややり方は、一人一人違うはずなのですが、一律なやり方では、一人一人の学びのプロセスを尊重することはできません。
かつて学校は、できるだけたくさんの子どもたちに効率よく知識を授けるべく存在していました。
昔は、先生と呼ばれる人は、その知識を授けることができる限られた人でしたので、
先生の話すことを、みな黙って静かに聞かなければ、その知識を享受できませんでした。
また、教科書や本などを読んだり、先生が言ったことや書いたことをノートに書き留めたりするためにも、文字の読み書きをマスターしなければ、学びに接することが困難だったのも事実です。
けれども21世紀の今、知識を得たりスキルを身に付けるために必要な情報は、あらゆる媒体から得ることができる時代です。
昨年、2度の米国視察で痛感したのは、「教師に求められる役割は、この10年で大きく変わった」ということでした。
米国の学校を訪ねると(特別な学校ではありません。私が取材するのはいつも、ごく一般的な公立学校です)、そこでは先生は、「授業をする人」ではなく「学習活動のプログラムを組み、子どもたちの学びをサポートする人」です。なぜなら、「学び方は一人一人ちがう」から。
さて、私の職場であるアンダンテ西荻教育研究所では
子どもたちは個々に、先生と一緒に、一人一人違うやり方で、学習を進めています。
統一の教材を使っているわけではないし、固定のカリキュラムがあるわけでもありません。
学校での学びに何かしらの困り感があってここにきている子どもたちなので必然的にそうなるのですが、
そもそも一人一人は違うのだから、その子一人一人に合った学習の進め方が一番効果的だというのは、障害云々、特別支援云々以前の話かもしれません。
学校の教室にいる子どもたちも、千差万別。
だから、UDL(学びのユニバーサルデザイン)の考え方が学校の先生方に広がってほしいと思っています。今年も、地道に伝えていきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正月太りは、背中に来る。。。
↓↓↓
★この記事を面白いと思った方、当ブログを応援してくださる方は、
【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
*当ブログ上の情報およびコンテンツの著作権は全て筆者に帰属します。
*トラックバックは歓迎♪(スパム防止のため承認制にしております。投稿後TBが反映されるまで少々お時間がかかりますのでご了承ください
- 2024年12月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2016年8月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月