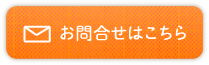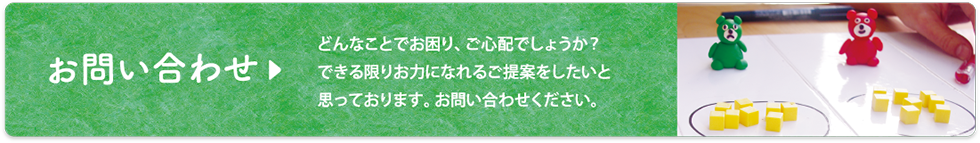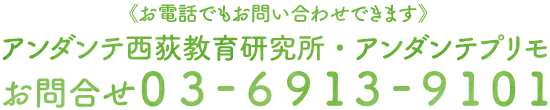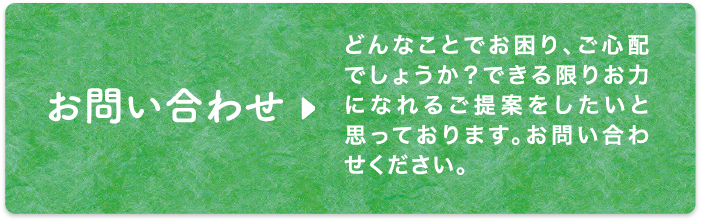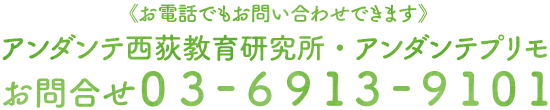新しい記事
- 2024.12.17 スタッフを募集中です。(株式会社リップルズ)
- 2023.12.20 金子は外でどんな仕事をしているのか?:アンダンテBackyard⑩
- 2023.11.15 アンダンテではどんな教材使ってる?:アンダンテbackyard⑨
片付けの苦手な子と片付けの作戦を立ててみた <苦手攻略大作戦>レポート5
<苦手克服大作戦>に参加してくれたメンバーのうち、今回は「持ちものの整理整とん」を目標に掲げた高校生がどんな「作戦」を立てたか、書きたいと思います。
「持ちもの」といっても、漠然としているので、まずとっかかりとして、一つに限定しようということにしました。かばんの中? 机の引き出し? それとも。。。。
「来週、親戚がうちに来るので、自分の部屋を片付けたいです」
ということ。では、次に、なぜ片付かないのかその原因を話し合ってみました。
その結果、わかったこと。
しまう場所のキャパシティに対して、モノの量が多すぎる!
モノを「人」、しまう場所を「家」にたとえると、彼いわく「家が足りないどころか戦場も同然で、大量の難民が発生している」らしいです。
きいていくと、どうやら彼は「捨てられない」一方で、モノがどんどん増えていくので、「入らない」→「出しっぱなし」→「山積み」・・・・になってしまっているようなのです。
ならば、混乱状態になっている箇所を整理し、難民(モノ)が帰るべき家(スペース)を確保して、戻していきましょう。・・・・残念ながら、彼の部屋で一緒にやれる課題ではないので、今回は話し合って方法を考えることしかできませんが、次のような作戦を立てました。
- 「①いつも使うモノ」「②ふだんは使わないが、とっておく必要あるモノ」「③要らないモノ」に分類する。
- ③を処分(捨てる。あげる。寄付)して、②を保管する場所を確保する
- ①の場所を見直す
さらに話を進めていくうちに、趣味(?)で作ったプラモデルをしまう場所がなく、部屋中に散乱している状態らしいということがわかってきました。また、学校の教科書類が棚に入りきらずあふれているということも。そこで、まず今日帰ってやることとして、
- 押入れにしまってある、もう使わない学習用具(小学校時代の絵の具や習字道具などなどが押し込んであるらしい)を処分し、そこにプラモデルを片付ける。
- 教科書を入れるラックをもう一つ用意して、おさめる。
という2つに絞りました。(本当は、衣類も大変なことになっているらしいですが、あまり欲張っても無理なので、衣類の整理は次の機会にまわそうということにしました)
さて、この<作戦>を実行に移したかどうか気になっていたのですが、先日彼のお母さんと電話で話す機会があったときに聞いてみたところ、
「えぇ、あっという間に、きれいに片付けてました」
おおおっ! すばらしい!
「・・・・・でも、再び散らかるのも、あっという間でした」
あはは(^ ^;)
この企画、継続したフォローアップが必要と痛感いたしました。
ちなみに、私も実は片付けられない女なのですが、彼との作戦作りで奮起して、8月最後の週末はキッチンの片づけをやりました! 期限の切れた調味料、もったいないととっておいたビンや容器や袋類、この先きっと使うこともないであろう景品などを処分したら、いっぱいスペースができて、行き場を失っていたモノたちが片付きました。この調子でパソコン周りやベッド周辺も片付けられたらいいんですが・・・・・まだ手つけてません(^ ^;)
この高校生君も私も、「片付ける」という作業を、いくつかのステップ(いる・いらない分類、処分、しまう)に分けて具体化したことで、行動に移せたようです。人によってどんな方法がぴったり合うかは異なります。日頃から部屋をきれいにできたり、モノの管理や整理整とんに苦労しない人は、こんなステップは必要ないのでしょうが、苦手な場合は、苦手の原因、うまくいっていない原因を明らかにして、対策を考えられるといいですね。たとえば、「どこに何をしまうかがわからない、覚えられない」場合は、引き出しに項目のシールを貼ったり、ファイルを色分けしたり。「モノを管理しきれない」場合は、モノの量を減らす、いつも使うモノは一箇所にまとめる、などなど・・・・・。
「自分に合った方法」を本当の意味で見つけるには、年単位で時間がかかります。いや、一生かかるかも・・・・などと、わが身を振り返って思ったりもします。でも、少しずつ少しずつ、改善していくことが大事なんですよね。
次回は、「リコーダーが吹けるようになる!」を目標にしてくれた子の話です。
さて、これから、ひと仕事、ふた仕事です。応援クリックもらえると、元気がもらえます。
↓↓↓
★この記事を面白いと思った方、当ブログを応援してくださる方は、
【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
- 2024年12月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2016年8月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月