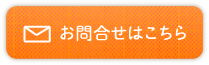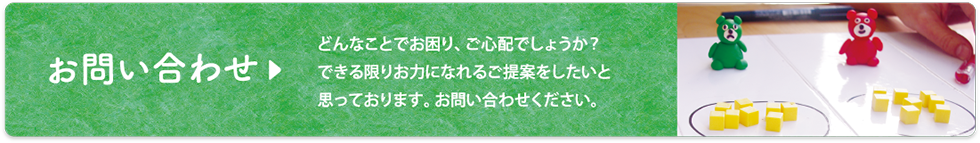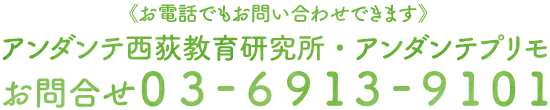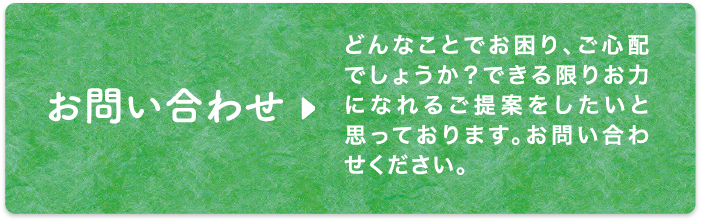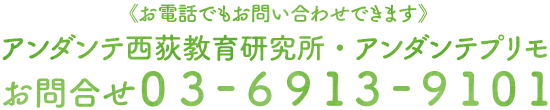新しい記事
- 2024.12.17 スタッフを募集中です。(株式会社リップルズ)
- 2023.12.20 金子は外でどんな仕事をしているのか?:アンダンテBackyard⑩
- 2023.11.15 アンダンテではどんな教材使ってる?:アンダンテbackyard⑨
閑話休題第4弾~オープンスペース校舎は失敗か?
閑話休題シリーズ。今日は校舎についての話です。
私が大学生だった頃、教育学の授業か何かで「オープンスペース」の校舎の小学校の実践を紹介した先生がいました。かつての日本の教育の「集団一斉指導」「画一的な校舎」「閉鎖的な教室」・・・・といったネガティブな側面を廃するために設計された、当時は画期的な校舎で、その後、この形態の校舎はひところちょっとしたブームを呼んだようです。
正確には「廊下と教室の間に壁のない校舎」というより、教室空間と「ワークスペース」という空間が一続きにつながっていると説明した方がいいのでしょうが、うちの地元でもいくつかそんなの学校があります。
これが巡回相談員たちの間ですこぶる評判が悪い。
なんたって、落ち着かない。教室が閉じられていないので、隣のクラスの声、どうかするともっと離れた教室の声まで聞こえてくるし、廊下を行き来する子どもたちや給食を運ぶ調理師さんの姿、あるいは参観している親御さん(「開かれた学校」は「いつでも参観日」を売りにしていることが多いし)なども目に入る。つまり、目からも耳からも刺激いっぱいで、注意力に問題を抱える子や、視覚から状況を判断する自閉っ子たちには、かなりきつい環境といえます。
実際、気がかりな子どもたちの様子を見てると、気は散るし、すぐ席立ちたくなっちゃうし、だから叱られる場面も多いし、騒がしくなると先生は大きな声を張り上げなきゃいけないし、ますます相乗効果になっちゃって、やっぱり大変そう・・・・。
そんなこんなで「オープンスペース校舎はよくない!」という声があがってきているのですが・・・・
私思うに、オープンスペースが悪者ってわけじゃないのではないかと。
一斉画一授業への疑問、欧米の個別化教育を起点とするオープンスペースの理念は、悪くないと思うのです。
問題は、理念は置き去りでハードだけが乱立してしまったこと。手法だけが一人歩きするメソッドと同じかも。旧来のスタイルの学校教育に異を唱えるためできたはずの新しい器で、やっていることは旧来通りの一斉授業。それも、先生1人に40人の子どもたち。そりゃぁ、刺激いっぱいの開かれた空間で、「ハイ、先生に注目!」は無理があるのではないかと。
オープンスペースが悪いのではなく、オープンスペースをいかす使い方ができていない。うまくいっていないところは、ハードとソフトの不一致が、新たな問題を生み出しているのではないでしょうか。
もし私が、あの素敵な空間を自由に使わせてもらえるなら、子どもたちに、どんな学びを提供できるだろう? そんなことを夢想してみます。
先生の話を聞く時間は最小限にして、個々に課題に取り組んだり、ペアやグループでの作業など、様々な活動を織り込めば、刺激に反応しやすく、じっとしているのがつらい注意集中の時間が短い子どもの強みを生かし弱さをカバーする学習活動ができるかな。
教室とワークスペースをいくつかのコーナーにわけ、場所ごとに活動を設定すれば、視覚優位の自閉っ子たちも理解して取り組みやすい学習環境にできるかもしれない。
個々の活動を重視する形の学習、・・・・オープンスペースの校舎が目指したものを形にするなら、講義型の一斉授業を最小限にして、ひとりひとりの能力を生かせるあんなこと、こんなこと・・・・アメリカやスウェーデンで見た学校の風景も頭をよぎります。
って、私が夢想しても、しかたないんです。私、学校の人間じゃないので。
確か大学の講義で紹介した先生は、「校舎から学校を変えていくんだ」というようなことをおっしゃっていました。
今ここで、オープンスペースはよくないというのではなく、せっかくの素敵な校舎を最大限生かせる教育を、ソフトの面から変えていってほしいと、願っています。
それと、オープンスペースじゃなくっても、一斉型、画一型の教育を脱することは可能・・・・ですよね?
風邪で寝込んでいる間に、一瞬1位まで上がったと思ったら、ずるずる10位までランキング転落しました。今後の動向は皆様しだいです。応援よろしくお願いします。
★この記事を面白いと思った方、当ブログを応援してくださる方は、
【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
- 2024年12月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2016年8月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月