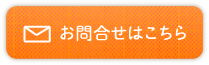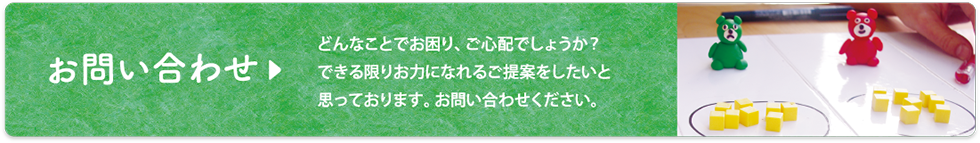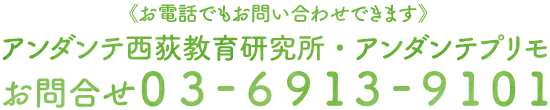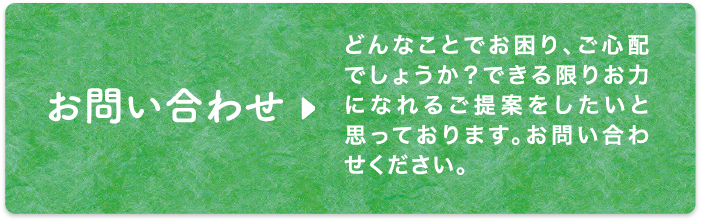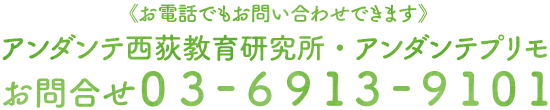新しい記事
- 2024.12.17 スタッフを募集中です。(株式会社リップルズ)
- 2023.12.20 金子は外でどんな仕事をしているのか?:アンダンテBackyard⑩
- 2023.11.15 アンダンテではどんな教材使ってる?:アンダンテbackyard⑨
子どもの「暴言」に真っ向対決しない。(3)
「暴言」などの表面的な行為と対決するのではなく、背景にあるものと向き合わなければ、と思います。
でも、「なんでそんなこと言うの?」と当人に尋ねたところで、本当の理由を話してくれることは、まずないでしょう。わからないから、うまく話せないから、「うるせー!」なのですよね。
だから、察してあげられるかどうか、にかかっているような気がします。大人の「思い込み」ではなく、日頃からの観察と、正しい知識に裏付けられた想像力を総動員して。その子が本当は何に困っているのか、本当は何を心配しているのか、本当は何がイヤなのか、ピタリ当てられたら、きっと子どもにも伝わります。「僕のこと見ていてくれてるんだ」「私のこと、わかってくれてるんだ」と。大げさなことではなくても。
前回の例で続けましょうか。「今日はこれをやるよ」と伝えたら、「やだ!」と返ってきた時、「なんで?」と聞いてあげて、もしも「だって~~なんだもん」と理由を話してくれれば、そこから交渉の余地が出てきます。一方的な説得ではなく、子どもの言い分も聞いたうえでの「交渉」。それがコミュニケーション力を育む基本ではないでしょうか?
でも「やだ!」を通り越して、いきなり「うるせー、ばか」だったら?
「対決しない」と強調していますが、もちろん、「暴言」を良しとするつもりはありません。「そういう言葉には応じません」という毅然とした態度で「乱暴な言葉は認めない。人を傷つける言葉は許さない」というオーラだけは放ちつつ、さらっと、淡々と、静かに応じたいものです。踏み込むのはその裏側。「暴言」の背景にある子どもの気持ちに向き合い、寄り添う・・・・。(namiママさんのブログで最近キーワードになっている「母性と父性のバランス」って、うまく言い当ててるなあと思いますね)
「やだ!」あるいは、その展開形「うるせー、ばか」の背景は?と探ってみましょう。
○この子にはちょっと難しい課題だな。だからイヤなのかな?・・・・と見当をつけたなら、「だいじょうぶ。これちょっと難しいかもしれないけど、先生がゆっくり教えながら一緒にやるから、できるよ」と言ってみる。それで「一緒にやって課題をこなせた」という成功体験を得られれば、その子は一つ獲得するでしょう。「難しいかも、自分にはできないかも」という課題を渡されたときに、「うるせー、ばか」ではなく、「わかんないから、教えて」とか「難しい問題はとばして、あとで先生とやってもいい?」という言葉を。
○なんかいつもより疲れてるのかな?眠そうだし。・・・・と気づいたなら、「今日プールがあったの?」ときいてみる。理由を子どもに確かめることができれば、お互いに納得の上で「それで疲れてるんだね。じゃあ、今日は半分だけにしておこうか」と妥協できるでしょう。その子はまた一つ獲得するでしょう。疲れていてがんばれないとき、気分がのらないとき、「うるせー、ばか」ではなく、「今日は運動会の練習でくたくたなんだ」とか「こんなにたくさん、無理だよ。少し減らしてくれない?」という言葉を。
理由を聞いてもらえる。察してもらえる→「~~なのかな?」「だったら、こう言おうね」と、暴言に代わる適切な言い方をモデルとして示される→その言い方を、その子が実践してみる→本人にとっていい結果をもたらす→その子の言葉として取り込まれていく。
そんな好循環を作っていきたいのです。
自分の心に余裕がないとできませんね。
この記事を面白いと思った方、当ブログを応援してくださる方は、![]() ←本日も1クリックをよろしくお願いします。【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
←本日も1クリックをよろしくお願いします。【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
*当ブログ上の情報およびコンテンツの著作権は全て筆者に帰属します。
*トラックバックは歓迎♪
- 2024年12月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2016年8月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月