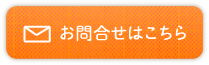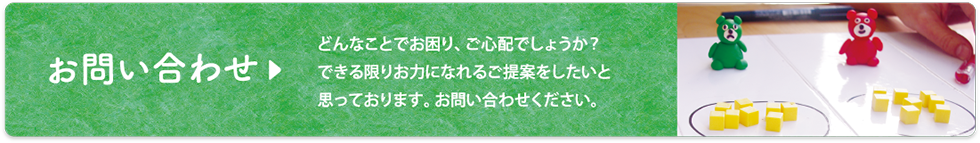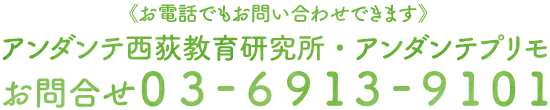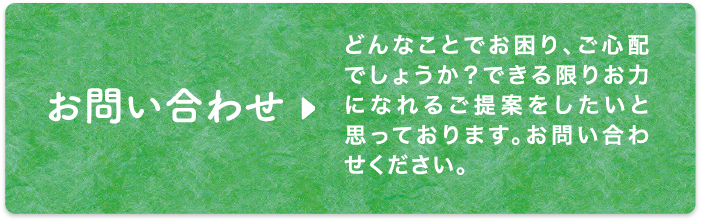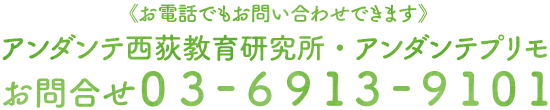新しい記事
- 2024.12.17 スタッフを募集中です。(株式会社リップルズ)
- 2023.12.20 金子は外でどんな仕事をしているのか?:アンダンテBackyard⑩
- 2023.11.15 アンダンテではどんな教材使ってる?:アンダンテbackyard⑨
癇癪(パニック)対応の原則:苦手をHELP!大作戦➄
思い通りにならないとき、想定外のことが起きたとき、苦手な場面や我慢しなければならない状況などでストレスがキャパを越えてしまったとき、大きな癇癪(パニック)をおこしてしまうお子さんたちがいます。一見わがままやしつけの失敗と誤解されがちですが、発達の凸凹に起因する癇癪は、本人が自分で感情を制御できるキャパシティを越えてしまった時に起こるものなので、どんなに予防線を張っていても避けられないことがあります。対応する親御さんは、どっと疲弊しますね。
それでも、適切な対応を積み重ねていれば、年齢とともに少しずつ癇癪の頻度も程度も軽減していくことが多いです。もし、年齢が上がるごとに癇癪がひどくなっている場合は、知らず知らずのうちに、周囲が誤った対応を取っていないか、振り返ってみる必要があるかもしれません。
ざっくりとした原則は、こんな感じです。
➀お子さんがギャーッとなる(癇癪発生!)
⇩
➁クールダウンできる環境を作る(静かな場所に移動する、周りの人を遠ざける等)
⇩
➂落ち着くまで静かに待つ(黙って寄り添う、距離を置いて見守る等) ☚ココが重要!!
⇩
④落ち着いたら、話を聞く(「何が嫌だったの?」「そういう時は次からこうしようね」)
これを繰り返し積み重ねていくと、癇癪の代わりにことばで伝える力が育まれていきます。その際、➂「落ち着くまで静かに待つ」が、実はすごく重要なんですが、うちのスタッフも、慣れない新人の時はここを抜かしてしまいがち。このステップを飛ばしてしまうと、こうなります。
➀ギャーッとなる
⇩
➁クールダウンスペースへ
⇩
➂そのままギャーッとなっている子に「どうしたの? ○○が嫌だったの? じゃぁこうしようか」
(なだめすかして落ち着かせる)
その結果、「ギャーッとなったら大人が対応してくれて、要求が通ったり自分のストレスを取り除かれたりする」という好ましくないパターンを脳が覚えてしまいます。
だから、ギャーッとなっている間は、じっと我慢です。嵐は必ず通り過ぎますから、待ちましょう。お子さんや周囲の安全を確保しながら心の中で時間を計るのもおすすめです。そして、嵐が過ぎ去ってから「どうしたの? ○○が嫌だったんだね。でもしかたなかったね。気持ちを落ち着けられて偉かったね」です。そのようにして、「落ち着いて、言葉で伝えれば、要求が受け入れられたりストレスを回避する方法を一緒に考えたりしてもらえる」という好ましいパターンを何度も経験させることが大事なのです。
- 2024年12月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2016年8月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月