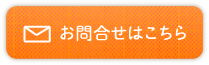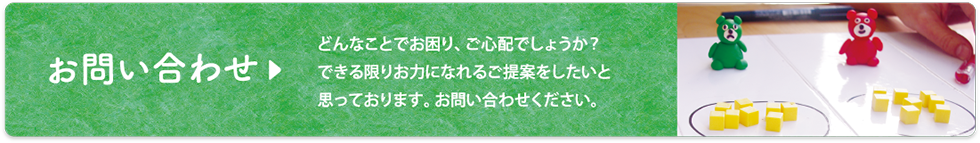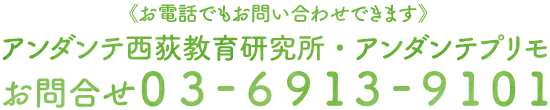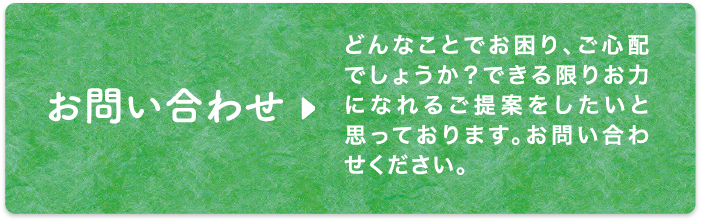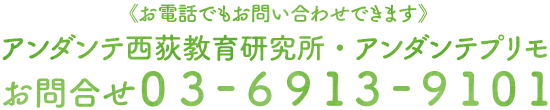新しい記事
- 2024.12.17 スタッフを募集中です。(株式会社リップルズ)
- 2023.12.20 金子は外でどんな仕事をしているのか?:アンダンテBackyard⑩
- 2023.11.15 アンダンテではどんな教材使ってる?:アンダンテbackyard⑨
板書とノート取りで配慮してほしいこと
前回、書くことにいっぱいいっぱいになって、理解できなくなる子もいるという話をしました。
読み書き障害の場合はもちろんですが、注意・集中の切り替えの苦手な子や、不器用な子、同時作業の苦手な子など、板書をノートに写すことが負担になる子って、けっこういるんじゃないかと思います。
ということで、本日は「板書とノート取り」のインクルージョン。
1 ノートに写させるのは「必要不可欠」な部分に絞る。
たとえば、「問題」を提示して「答え」を子どもたちに考えさせるとき、問題もノートに書き写させる必要があるのかどうか。 黒板に書かれた算数の計算問題、写すだけでイヤになってしまっている子、いますよね? 事前にプリントにしておけば、「答えを出す」ことに集中できるかもしれません。同じ意味で、ワークシートも効果的に使ってほしいものです。
2 書く時間と話を聞く時間、考える時間をわける。
書きながら聞く、書きながら考える、といった「ながら」作業ができるのは、「書く」ことが自動化されている必要があります。(自動化・・・いちいち考えなくても手が、体が、覚えている状態ですね。) でも、読み書きに困難のある子は、「書く」という行為に全力を注がなければいけません。逆に、聞くことや考えることに集中しにくい子も、動揺のことがいえます。 だから、子どもたちが書いている最中に説明をしたり、書かせるだけで考える時間を与えなかったりすると、「写しただけ」で終わってしまう子がでてきてしまいます。
だから、書く、聞く、考えるが同時作業にならないよう配慮してあげてください。
3 書くのに時間がかかる子には、書く時間を確保する。
事前にプリントを渡しておくとか、大事なことは黒板ではなく紙に書いておいてあげて後からでも見られるようにしておくとか、ちょっとした配慮で「書く」ことに弱さを抱えるこのストレスを減らすことができます。
板書を写さない、ノートをとらない=「学習態度が悪い」と見なされがちですが、いま一度、授業の中の「書く」を見直してみていただけたら嬉しいです。
一方、「書く」ことは、思考を活性化するためにとても大事な要素にもなります。「書く」作業をどう取り入れるかも、考えてみたいと思います。
眠い目をこすりこすり書きました。変な文になってるかも・・・。応援クリックよろしくお願いします♪
↓↓↓
★この記事を面白いと思った方、当ブログを応援してくださる方は、
【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
*当ブログ上の情報およびコンテンツの著作権は全て筆者に帰属します。
*トラックバックは歓迎♪
うちの職場には。なぜかA型がいない。すぐモノが散らかる。
- 2024年12月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2016年8月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月