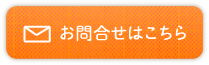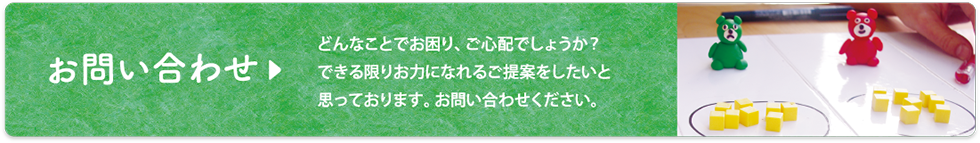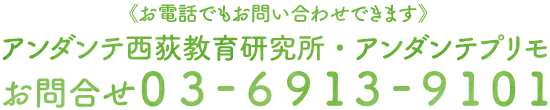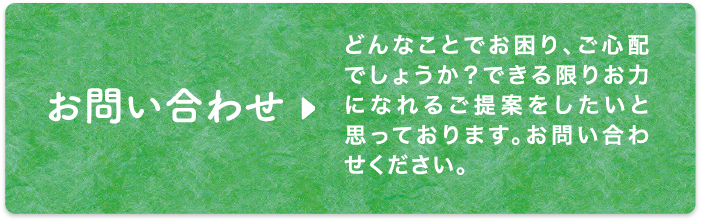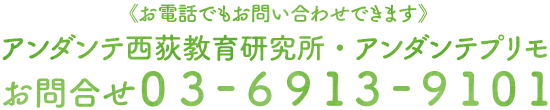新しい記事
- 2024.12.17 スタッフを募集中です。(株式会社リップルズ)
- 2023.12.20 金子は外でどんな仕事をしているのか?:アンダンテBackyard⑩
- 2023.11.15 アンダンテではどんな教材使ってる?:アンダンテbackyard⑨
授業のもっとも重要な「型」
授業の最初に、その時間の「めあて(目標)」を子どもたちに伝えていますか?
いわゆる「研究授業」のときは、ほとんどの先生が、やっているんですよね。
先日のぞいた授業も、その先生は
わらぐつの中の神様
今日の課題 おみつさんの人がらと気持ちを読み取ろう
って、黒板に書いてから、内容に入っていきました。
でも、ふだんの授業で、授業の最初に必ずテーマ名とあわせて「めあて」を書いて示していらっしゃる先生の割合は、かなり低いようです。
これが、ニューヨークの小学校の授業を視察したとき、気づいたことの一つでした。見学した二つの学校の先生方は皆、その時間に何を学ぶのか、何ができるようになってほしいかを書き、子どもたちに確認してから授業を始めていました。そして、授業の終わりには、「○○についてわかったか」「○○のやり方がわかったか」と、子どもたちに振り返らせていました。
実は、このはじめの1分、もしかしたら30秒程度のひと手間で、とても大きな差が出るのです。
「めあて」を示すことは、「今から何について話されるのか」「意識をどこに向けて見る(聞く)べきなのか」「何を覚えなければいけないか」「何を考えなければいけないか」などなどを、明確にすることでもあります。これは、学習の「はじめの一歩」です。
このプロセスは、注意散漫で集中力の持続が困難な子や、覚えることが苦手な子の負担を軽減できるでしょうし、もちろん、すべての子どもにとって、同じ1時間の授業でも、目的意識が明確になっているか否かで、モチベーションがだいぶ違うでしょう。
ある校長先生が新卒採用の先生に、歌舞伎役者の言葉を引いて「授業も“型”が大事なんだよ」と説いていらっしゃいました。「型破り」とは、基礎となる一定の「型」をきちんと身につけ、「型どおり」ができた上でできること、だと。
はじめに「めあて」を書いて伝える。最後に、「めあて」について振り返らせる。
これはきっと、授業の「型」のひとつでしょう。
毎日、毎時間、どの授業でも、ぜひ習慣にしてください。
だって、「めあて」を伝えることは、子どもたちに希望を語ることですもの。
「先生は、今日この時間、きみたちに、こんなことを学んでほしいんだよ。こんなことが、できるようになるよ」って。
もちろん、子どもたちにプレッシャーを与えたり、わからない子、できていない子を責めるためではありません。最後に「めあて」について振り返るのは、次の希望につなぐため。
もしも、目標に届かなかった子がいたとしたら、先生はその子を非難せず、原因を探って、自身の教え方を検証したり、支援の手立てを考えたりしてください。
授業のユニバーサルデザインは、「あたりまえのこと」「ちょっとしたこと」をきちんとやることから。このブログの原点にに返ってみました。
なるほどな、と思ったら、クリックしていってください。順位のアップダウンより、読んでくださった方の率直な反応を知りたいです。
↓↓↓
★この記事を面白いと思った方、当ブログを応援してくださる方は、
【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
*当ブログ上の情報およびコンテンツの著作権は全て筆者に帰属します。
*トラックバックは歓迎♪
- 2024年12月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2016年8月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月