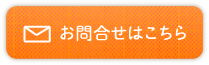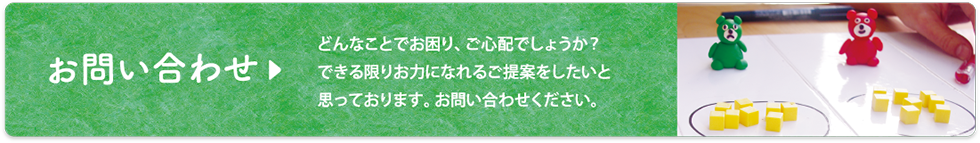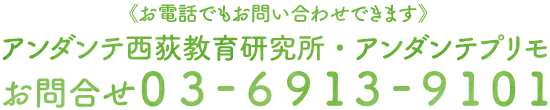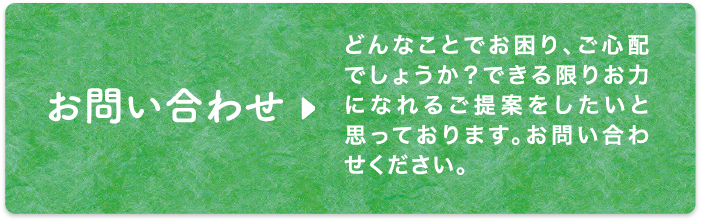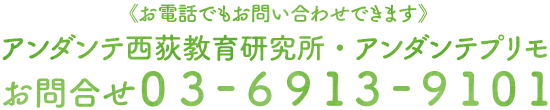新しい記事
- 2024.12.17 スタッフを募集中です。(株式会社リップルズ)
- 2023.12.20 金子は外でどんな仕事をしているのか?:アンダンテBackyard⑩
- 2023.11.15 アンダンテではどんな教材使ってる?:アンダンテbackyard⑨
日米、天と地の差、ってわけじゃない。できることから変えていくだけ。
先ほど帰国しました。
ニューヨーク報告第4弾は、もう少しだけ、記憶の新しいうちにニューヨークの公立小学校P.S.166の話を書き留めておきたいと思います。(ニューヨークレポートまとめ読みは→こちら)
ランチタイムの雑談で、先生方にいろいろ聞かれました。
お決まりですが、
「1学級の人数は?」
もう慣れっこの反応ですが、40人定員と答えると、欧米では驚愕されます。ニューヨークは「20~25人程度」ということになっているけど、前回書いたように、この学校は評判を聞いて入ってくる子どもも多く、30人ぐらいいるクラスが多いようです。
「そんなに人数がいて、学習や行動に課題を抱える子に対応できるんですか?」
いえ・・・・。それが今大きな問題で、だから私がここに来ているんです。。。
オウ・・・!(納得のため息)
「先生の授業スタイルは? ワークショップ型の授業をする先生は多い?」
ん~、ざまざまな手法や工夫を凝らした授業をしている先生もたくさんいるけれど、学級人数が多いから、どうしても一方向的な授業になりがち・・・・。ここまで子どもに学びの主導権を渡すやり方を日常的に取り入れるのは、ちょっと日本の先生には勇気がいると思う・・・・。というようなことを言ったら、やっぱり
オウ・・・・。とうなずかれました。
「それで、日本ではSAを取り入れている学校はどのくらいあるの?」
ないです。というか、たぶん日本でSAを知っている人間は、まだ私1人ですから。
オウ・・・・。
「脳科学の見識は、どのくらい教育に活用されている?」
それもまだまだ・・・・これからです。
オウ・・・・。
てな感じで、議論、非常に盛り上がらなかったです・・・。
でも、ね。人数のことにしても、授業のスタイルにしても、「学習」のとらえかたにしても、アメリカだって10年、20年前は似たようなものだったのです。
ここで見てきた「学び方はいろいろ。自分に合ったやり方、覚え方で」という方針も、私が個別指導でその子に合ったやり方をすすめても「学校で習ったやり方と違う」と、抵抗する子どもたちがいることを話すと、 「私が子どもの頃も、そうだったわ」 と、先生たちは話していました。あるいは、ワークショップ型授業を取り入れた際も、子ども主体の学びの風景に「何だ、この授業は! 先生が教えていないじゃないか」という批判をうけることもあったとか。それでも、実践を積み重ねて
この人たちは、変えてきたんだ。
そう思いました。
海外に行くと、日本と比較して「だから日本はダメなんだ」という人(特に日本人)がよくいるのですが、私は決してそうは思いません。違うのは当然だし、日本の教育の方が優れている面もたくさんあります。また、アメリカの教師や子どもたちが置かれている教育環境が恵まれているともいえません。お客としての私が見たのは、「どこに出しても恥ずかしくない」先生の授業に違いないし、アメリカの先生の力量も一人ひとり差があることでしょう。学校も教師も数字での評価にさらされ、割に合わないたくさんの仕事を抱え、さらには免許更新のための研修もいっぱいあって、大変な思いをしているのは同じです。
そんななかでも、できることから変えていったんだな、と。
日本の先生だって、きっと。
今回の取材の主目的であるSA(Schools Attuned)については、ちゃんとしたところにちゃんと書きたいので、ここではあえて触れませんでした。とりあえず、見てきた光景と感じたことをそのままご報告した形なので、主観が多々入っていますことを、ご承知おきください。
次回はCTTについて、少し補足です。
明日は、半月ぶりに出勤。子どもたちに会えるのが楽しみです。帰宅して、荷物を解いて、いちばんにしたことがブログ更新。こんなワーカーホリックな私に、なぐさめのワンクリックを。
↓↓↓
★この記事を面白いと思った方、当ブログを応援してくださる方は、
【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
- 2024年12月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2016年8月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月