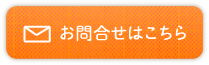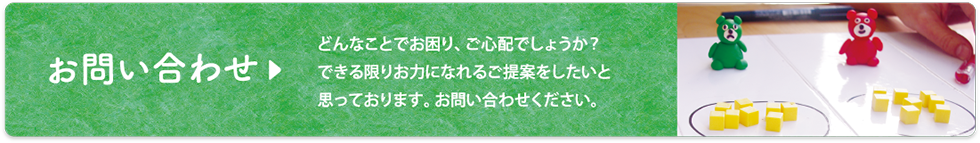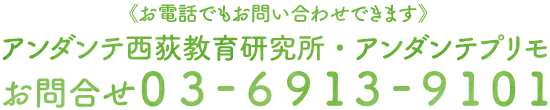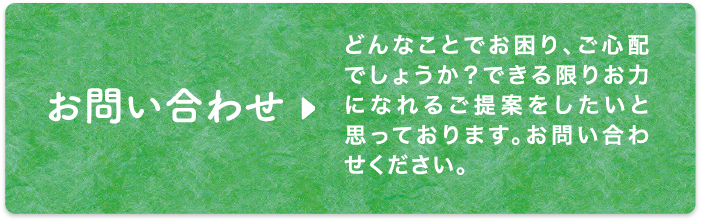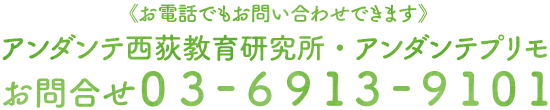新しい記事
- 2024.12.17 スタッフを募集中です。(株式会社リップルズ)
- 2023.12.20 金子は外でどんな仕事をしているのか?:アンダンテBackyard⑩
- 2023.11.15 アンダンテではどんな教材使ってる?:アンダンテbackyard⑨
文部省の「LDの定義」も10年目かぁ・・・~はるえもん試験勉強中 その2
もう、何度となく目にし耳にしてきた、文部省によるLDの定義(1999)
「学習障害とは、基本的に全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す状態を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない」
当時は、「IQは平均以上あるけれども、読み書きや計算ができない子がいるのだ」ということに文部省がある意味お墨付きを与えたのは、画期的なことだったと思います。でも、その一方で、「レッテル貼りだ」と抵抗感を持つ人もいたし、定義があいまいさを残すだけに、学校でつまずく子は誰でも彼でもLDとみなされてしまうリスクもありました。
それから10年近く経つ今、LDって何だろう?って、あらためて思います。
ところで、いわゆる「教育定義」と呼ばれるこの定義の英語表記はLearning Disabilitiesなのですが、医学領域ではLearning Disordersです。disabilityは「能力の障害」、disordersは「機能の障害」という感じですね。それで、前回の発達障害の定義同様、やはり医学的な定義と文科省の定義は多少ずれがあります。
DSM-Ⅳ-TRでは、「学習障害」は読字障害、書字表出障害、算数障害に限定し、教育定義の「聞く」「話す」にあたる受容-表出混合性言語障害と表出性言語障害は「コミュニケーション障害」としています。ICD-10も同様、「学力(学習能力)の特異的発達障害」として特異的読字障害、特異的書字障害、特異的算数能力障害、「会話および言語の特異的発達障害」として受容性言語障害、表出性言語障害に分類しています。
学習障害が学齢期に入ってから判断可能になることを考えると、診断基準の分類であるDSMやICDが言語の障害と学習障害を切り離すのも理解できます。
ですが、教育現場では、その子のつまずきの原因がどこにあるか、どんな支援が必要かを考えるとき、言語の問題を切り離して考えるわけにはいきません。だから、文部省の定義が医学定義の学習障害とコミュニケーション障害をごちゃ混ぜにしてしまっているのも、わかるような気がするのですが・・・・
それを言うなら、たとえばADHDの子たちの「注意」や「衝動性」の問題だって、学習には大きな支障をきたしていますし、運動機能の問題を抱える子だって、そうです。
現場では、これらの定義と実際の不一致感を覚えることもあるのではないか、そんな気がします。少なくとも私が最近もっぱらメル・レビーンの理論に依拠するのは、そのためです。
試験勉強というよりも、自分なりに勝手に解釈したり、考えが脱線していくから、覚えられないんだろうなぁ。。。
次回は、ADHDと高機能自閉症・アスペルガー症候群の定義の予定。
応援クリックもらうと、素直にがんばります。
↓↓↓
★この記事を面白いと思った方、当ブログを応援してくださる方は、
【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
- 2024年12月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2016年8月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月