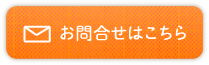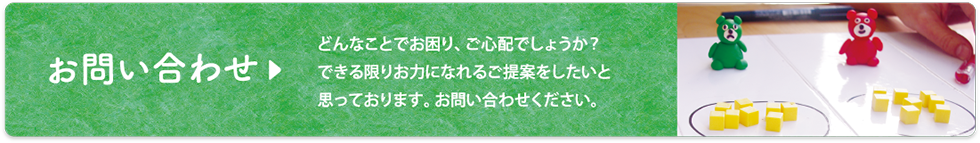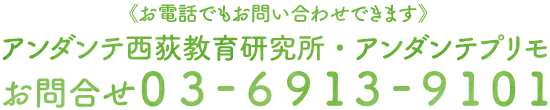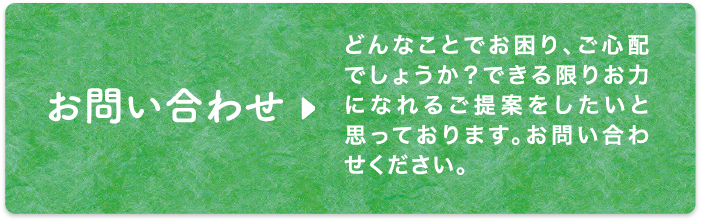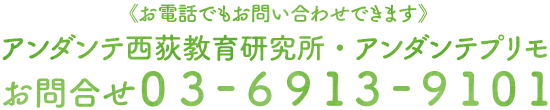新しい記事
- 2024.12.17 スタッフを募集中です。(株式会社リップルズ)
- 2023.12.20 金子は外でどんな仕事をしているのか?:アンダンテBackyard⑩
- 2023.11.15 アンダンテではどんな教材使ってる?:アンダンテbackyard⑨
ルールって何だ?(4)
話は戻って、ルールの明快な教室、ルールのあいまいな教室について考えてみることにします。 →「ルールって何だ?」(1)、(2)、(注)、(3)から続いています。
なんでもかんでも細かくルールにするのは複雑で分かりにくく、かつ窮屈になるのはいうまでもありませんが、自由度が高すぎ「最低限の秩序」ができていない社会は、かえって生活しづらいものですよね。
そこで、複数の人が集まって過ごす場には「自然と」ルールが生まれます。そういうものは、たいがい「暗黙の了解」で成り立っています。
ところが、発達障害を持つ子たちの中には、この「自然発生的なルール」や「暗黙の了解」を理解するのがとても難しい子どもがいます。また、理解できても、他のことに注意が向いてしまうと、ルールのことなんか頭から抜けてしまう子もいます。
だからこそ全体へのアプローチが鍵を握るのではないか・・・ルールの明快な学級作りが、彼らにとって「支援」となりうるのではないか・・・・最近、私はますますそんなことを考えています。
冒頭の「授業中に関係ないことを勝手にしゃべりだす子」の例に戻って考えて見ます。
もしもそのクラスに「発言するときは手を挙げる。あてられた人が話す。他の人は話をきく」というごく当たり前のルールが明確で、クラスの子どもたち全体にきちんと浸透していれば・・・・。
もしもルールの理解が困難で、手を挙げずに勝手に発言してしまったのなら、「言いたいことがある人はどうするんだったかな? そう、手を挙げて、あてられたら話そうね」と教えていきます。また、注意が他所に行ってしまって関係ないことを話してしまったのなら、「今は何の時間かな? その話は休み時間にしようね。さあ、お友達の発言をよく聞いてみよう」と、今すべきことを思い出させます。きっと、その子は周りを見て「あ、そうだった!」と気づくことができます。
ところが、例えば「手を挙げて発言する」というルールがあいまいで、周りの子どもたちも適当に言いたいことを言っていいクラスだったら? 挙手無しの発言でも、なんとなく反応してしまう先生も見かけます。先生が求めていた「いい発言」だったら、手を挙げてなくても採用されてしまったりもします。でも、場の読めない子やタイミングのつかめない子は「勝手に」「関係ない発言」をすることになってしまいます。「今何の時間?」と問われて周りを見ても、他の子たちだって手を挙げずにしゃべっているわけですから、これもわかりにくい・・・。
ルールというのは、子どもたちの行動を制限するためのものではなく、子どもたちが自らの行動を判断するための手がかりとなるものであるべきなのですね。
同じ意味で、行動の判断の手がかりが「先生の指示や態度」になってしまっているクラスも、発達障害の子どもたちには(というか、他の子どもたちにも、たぶん)、ルールを学びにくい環境なのではないでしょうか。
この記事を面白いと思った方、当ブログを応援してくださる方は、![]() ←本日も1クリックをよろしくお願いします。【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
←本日も1クリックをよろしくお願いします。【にほんブログ村 教育ブログ】へリンクし、人気ランキングの1票となります。
*当ブログ上の情報およびコンテンツの著作権は全て筆者に帰属します。
*トラックバックは歓迎♪
- 2024年12月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2016年8月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月